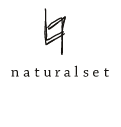皆さんこんにちは。
久しぶりにメイキング紹介のエントリをやってみようと思い、数日掛かりで原稿を書きました。
製品はタイトルにもあるすっきりレザーショルダーバッグの黒です。
今回はこれまで省いていた細かいところもフォローしたので、写真が全部で84枚にもなってしまいました。
ご自身でクラフトなさる方にも、またクラフトはしないけど、製法に興味がある方にも楽しんでいただけると思います。
どうぞご覧になってください。
まずは元の革をカットするところからです。
80☓150センチの大きめテーブルの上を片付けて、カッターマットを敷いて、革をひろげます。
イタリアの植物タンニンなめし、牛脂などの脂を加えるバケッタ製法でなめされた、グレードの高い革です。
いい香り~~。

これに型紙をおいて、切り出します。
型紙の外周にそって目打ちなどでなぞって跡をつけて、型紙をはずしてから刃を入れる方法もありますが、跡をつけて→切ってだと、下の線からズレる確率が上がると思うので、私の場合は型紙にそって直接切ってしまいます。

切る道具ですが、一般的には左側の「革包丁」と呼ばれる専用の刃物を使うことになっていますが、小回りがきくほうが好きなので、右のオルファカッターを使っています。
よく見かけるカッターの刃先の角度は60度ですが、これは30度で、より鋭利です。軸が細くて持ちやすく、どんな型紙でもキレイにトレースできるので気に入っています。

胴板を切り出しました。
左右に3箇所ずつ、下の中央に1箇所、三角形の刻みが入れてあります。
2枚縫い合わせる際の目印にします。

では内布を切りましょう。
この製品の場合、外側の革と同じ型紙を共用しています。
布のように引っかかる素材の場合は丸い刃のカッターを使っています。

切り出したポケット布の周囲をアイロンで曲げておきます。

革タグの用意も忘れずに。
ブラウンの場合は焼き印だけですが、黒の場合は箔押し(はくおし)します。

ポケット大小ができましたよ。

これを内布の上に乗っけてマチ針で止めます。

ポケットを縫い付け、さらにダーツのところを縫い合わせます。
(ホントはダーツとは言わないですね。なんていうのかど忘れしました。以後、一応ダーツで通してしまいますので、正確な呼び方が必要な場合はお調べくださいm(_ _)m)

そして2枚縫い合わせて、内側完成です。

あ、軽くアイロンをあてて、形を整えておきましょう。

さて、それでは胴板にとりかかりましょう。
上の方でカットした段階では、3ミリ弱の厚みがあり、そのままでは厚いので、革の状態を見ながら薄く加工します。
通常だと2ミリくらいでしょうか、比較的硬めの時は気持ち薄くするときもあります。
その後、ダーツ(?)のところをカットします。

裏側をみてみましょう。
縫い線のところは、さらに厚みを減らして、表返したときにすっきり見えるようにします。これを革漉き(かわすき)と呼びます。
まず右のように外周を漉いて、次にダーツ(?)のところを漉きます。

ダーツのところは、カットされているラインよりもグッと内側まで縫いこむので、左のように奥まで漉いておきます。

縫うときに抵抗が少なくなるよう、ローラーで圧迫して折り目をつけておきます。

縁の部分は黒のクラフト染料で着色しておきます。

一箇所縫い終わったところです。
縫い始めの2目と、縫い終わりの3目が太くなってますね。
これは「返し縫い」の結果です。とくに最後の3目は、形を整える際にローラーで強くしごくので3回返してあり、その分濃く見えています。

ちょっとミシン関係のことも紹介しておきます。
奥に見えるの糸巻きから、ミシンに糸を来ていますが、途中、銀色のハコを経由してますよね。
これはナニかわかりますか??

中を開けると分厚いフェルトが入っています。
これに右側に見えるシリコンオイルをしみ込ませ、糸に付着させるのです。
これによって、分厚い素材を縫う際の針と糸の抵抗が減って、糸切れを防ぐことが出来るのです。
ナチュラルセットはゆっくり縫製するほうですが、速いスピードでじゃんじゃん作る大きなメーカーさんの現場だと、これは必需だそうです。(そうです。見たことないけど。)
オイル・・・と聞くと、しみになるんじゃないの?と思われると思いますが、これはなりません。大丈夫です。

さて、胴に戻ります。
縫ったばかりの革を表返すと、このようにモタモタっとした感じに見えます。
ではどうするか・・

今一度裏返して、リッパーで軽く切込みを入れ・・

ローラーでグリグリしごいて成形します。

すると、このようにスッキリなラインが出来上がります。

では、この2枚を縫い合わせていきましょう。

その前に、こんなコトしてます。というご紹介。
一番最初の工程で革を切り出す際、硬さやシボのより具合を見ながら、どれとどれをペアにするか決めるのですが、なんらかの方法で印を付けておかないと、取り違えの可能性が出てきます。
でも、裏にマジックなどで書いたにしても、胴の厚みを減らす(漉く)際に、一緒に削れてわからなくなってしまいます。
そこで、ダーツの縫い代部分に目打ちで印をつけるようにしています。ここだと縫ったあと、裏側に隠れてしまうので問題無いですね。

では縫い合わせましょう。

例の刻み目を合わせながら縫っていきます。
この革の場合、そうつるつるしてるわけでもありませんが、革同士を縫い合わせる場合、布に比べて上下がずれやすいので、手指や目打ちを使って補正しながら縫い進めていきます。

このダーツのとこは厚みがあることもあり、特にずれやすいです。
そんなときは目打ちをグッと深く挿して、ズレを防ぎつつ、革が滑らかに送られるように介添えしてあげます。

縫いおわりました!

表返す前に、曲線部分が綺麗に出るように刻みを入れます。

ひとまず表返した様子。
もこもこっとしています。

縫い合わせのところをローラーで丹念にゴリゴリして成形すると・・

すっきりしてきましたね。

胴が縫えたところで付属品に移ります。
ファスナーのつまみを作ります。
型をあてて目打ちで線を移します。

カッターでタテの線を切って・・・

上部を半円ポンチで切り離した後、カシメ用の穴を開けます。

外周は面取りしておきましょう。

黒いクラフト染料で着色。

ファスナーのスライダー(引き手)に通してカシメで留める際、綺麗に曲がるように、裏側の3分の2くらいを漉いて薄くしておきます。
漉いて白っぽくなった裏面も後で黒く塗っておきます。

ナチュラルマークを箔押し(はくおし)して出来上がりです。
焼き印だけでしっかり跡をつけるときは、250℃くらいでギュッと。箔押しの時は100℃くらいで、専用の銀色のシートを挟んでポンと軽く押します。

次は肩ベルトです。
長いものさしをあてて、18ミリの幅にカットします。
短いものさしを移動させながらだと、どうしても線がぶれてしまいますので、長いのに限ります。
工房には目的に応じて30センチ、60センチ、100センチ、150センチと4種類用意しています。
最初は前者の2コでスタートしましたが、必要に応じて買い足しました。
150センチのは1万円くらいしましたが、肩ベルトを切るとき「買ってよかったなぁ」としみじみ思います。

両端の面取りをします。裏側もやります。
 やはり、途中で切れずにフィニッシュできると気持ち良いものです(笑)
やはり、途中で切れずにフィニッシュできると気持ち良いものです(笑)

カット後、断面を黒く着色し、仕上げ材を塗って、軽く磨きます。
手前のは肩ベルト、奥のは余ったベルトをまとめるベルト通し用です。

ではでは、ファスナーに参りましょう。
多くの方には10センチ、15センチ、30センチといった、規定の寸法に整えられているものがおなじみだと思いますが、業者向けの切り売りのものを使っています。

周辺のパーツのアップ。
左が終わりのところを留める下留め。中央がスライダー、右はスライダーが抜けないようにする上留めです。

加工に入ります。
まず両端の「虫」を取り除きます。
この道具は喰い切り(くいきり)といいます。ホントに喰い切り!って感じのカタチをしてますよね。

綺麗に取れました。
なれないと布を切ってボロボロにしてしまいます。

お尻の方を止めます。
まず、ペンチのようなもので軽く閉じておいて、その後、木槌で軽く叩いてしっかり止めます。

スライダーを入れましょう。
そろそろと・・

ググッと・・

その後、両側に上留めを付けます。
コレは小さいものなので、ペンチの根本でグッと潰せばしっかり止まります。

取り出しましたのは革の裏に両面テープを貼ってこしらえた革テープ。。

お化粧するのですね。

同じ革テープではありませんが、おしりの方も革をはさみます。

その後、ぐるっと縫います。

おしりもですね。

ファスナーの下ごしらえの次はベルト類の加工です。
長いのが長い方、短いのが短い方、小さいのがベルト通しです。

ベルト通しは両端を薄くして、かつ、1.5ミリの穴を開けておきます。

この穴同士を小さなカシメで留めて輪っかにします。

長・短ベルトの端に本体に縫い付ける際の下穴を開けておきます。
ベルトに中央の型紙を載せて、右端の菱目打ち(ひしめうち)という道具で跡をつけ、左端のような状態にした後、跡に刃先を合わせてドン!とやると、右側のようになります。

ベルトの両端にステッチを入れます。
ステッチ無しもいいのですが、長い目でみると、微妙に伸びることもあるので、伸び止めの意味で入れています。
先日、どれくらい強いか試してみたところ、ベルト一本あたりに使う8番手のミシン糸4本(上糸と下糸☓2)で、11.5キロある職業用ミシンを吊り上げることが出来ました。ナイロンって強いですね~。

ミシン針も見てみますか?
このバッグを作るのには、3本の針を使います。
皆さんがご家庭で使うミシン針だと、9号、11号、14号、16号といった感じだと思いますが、このバッグで使うのは14号と19号と22号の3種類です。
胴板の周囲とダーツの部分はできるだけ針穴が目立たないようにしたいので、革用の工業用ミシンとしては異例の細さの14号、ベルトの両脇や、口周りにファスナーを縫い付ける時など、革を厚いまま縫うときは19号、ベルトの端に金具(美錠)をつけるときに革を2枚合わせて縫うときは22号を使っています。

左が14号、右が19号です。
ベルトの金具(美錠)をつけたところ。
ここは22号の針を使います。19号だと摩擦が大きくて、返し縫いした時に糸が切れちゃいますね。
あ、あと使っている糸は、ベルトや口周りは上糸8番、下糸20番、それ以外は上下20番です。
ご家庭で使う糸はジーンズの裾上げ用などの一番太いのでも30番ですからだいぶ太いですね。

さて、次はベルトを胴につける準備です。
ベルトの端に開けた穴と同様のパターンで胴側にも穴を開けます。

手縫い用の針に手縫い用の糸を通して、、これから縫い付けますよっ!

料理番組のような素早さで縫い終わりました!

長短ベルトが付け終わったら、予め作っておいた内布を入れます。
口周りは細い両面テープで仮止めしてあります。

さらに、こちらも作っておいたファスナーをあてがいます。
この仮止めも細い両面テープのお世話になります。

再度脱線。
まち針、皆さんは針山に刺してらっしゃいますよね。
私は針山だと、挿すときも抜くときも両手を使わないといけないし、なんだか偏った位置に刺してしまって抜きにくくなるので、プラスティックの容器の底にバッグ用の小さなマグネットをテープで止めたものをつくって、これにポンポンならべるようにして使っています。
針先が磁石に吸い寄せられて、なんとなく揃ってくれるので芳しいです。
 さて、下ごしらえが済んだところで口周りを縫いましょう。
さて、下ごしらえが済んだところで口周りを縫いましょう。
口周りを縫う動作は、これまでの工程の最終段階ということもあってか、業界では「まとめる」と呼ばれるようです。
「まとめる」には、こういうミシンを使います。
右側からニュッと伸びたウデの先に下糸のお釜が入っています。

それではスタート。
右側に見えるのは、縫い位置を決めるためのガイドです。

ベルトが付いているあたりは狭いので気を使います。
なお、一般的なメーカー品だと、こういう工程は失敗を誘発するし、第一、ベルトを付けてから縫製だと扱いが悪くて仕方ないので、ベルトは別パーツにしておいて、最後に取り付けるような構造にするケースが殆んどです。

ゴールは目前。

革バッグの縫製の場合、だいたい最後は4目から5目ほど重ねて縫って終わります。
返し縫いすると見た目が悪くなってしまいますからね。

糸の処理ははんだごてでチョンと焼いて切ります。
ハサミで切ると、なにかの拍子で抜けてほつれてしまいますが、化繊の糸を熱いもので焼き切っておくと、糸の端っこが小さく丸くなるので、抜け止めになるんですね。これは業界標準だと思います。

ベルトの穴あけ。
ベルトの下ごしらえ工程で済ませておいてもいいのですが、ここまで来てから、あるいは最後の最後に開けるのが好みです。
以前、開け忘れて発送してしまい、ご迷惑をお掛けしたこともありましたm(_ _)m

これでほんとに最後ですね。
ファスナーのスライダーに革のつまみをカシメで留めて終わりです。
お疲れ様でした。

工房の壁に吊るして眺めてみましょう。

ちょっと寄って。。

さらに寄って・・。

掛けたところ。

とまあ、こんな感じで作っています。
価値観はお客様それぞれですが、革の問屋さんや同業の作家さんからは、「安いですよね~~」と言われることがおおいです。
ファッションアイテムは、同じ用途の製品でも、メーカーのブランド価値によって価格が大きく異なりますので一概には言えませんが、多分、小売店さんへの「卸値」くらいの値段なのかなぁ。。と思っています。
それではこれにて終了です。
長い長いページにお付き合いいただいてありがとうございました!
興味を持っていただけましたら製品ページにもお立ち寄りください
すっきりレザーショルダーバッグ(黒)のページ